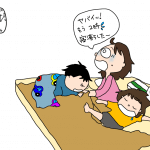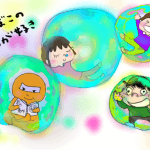パート主婦が直面する「103万円の壁」をご存知でしょうか?
妻の年収が103万円を超えると夫の所得控除が減ってしまい、結果的に損をしてしまうことから103万円の壁と呼ばれています。
パート主婦のみなさんは、この103万円を意識している方が多いと思います。
この壁が2018年の税制改正で見直されることになりました。
そこで、2018年から「どこが変わるのか?」「どんな影響があるのか?」にスポットをあてて、お伝えします。
税制改正の見直しで何が、どう変わったの?
まずは変わったことについてみていきます。
配偶者控除は103万円以下で据え置き

これまで、妻の年収(給与収入)が「103万円以下」の場合、夫の所得から38万円が控除されました。これが“配偶者控除”です。
2018年以降も、この「103万円以下」の条件は変わりません。
ただし、夫の年収(給与収入)が1120万円を超えると控除額が減額されるようになり、1220万円を超えると控除額がゼロになる制度が新設されました。
配偶者特別控除は201万円以下に

これまで、妻の年収(給与収入)が「103万円を超えた」場合でも、夫の所得から一定額が控除されました。
これが“配偶者特別控除”で、103万円を超えたらいきなり控除額がゼロになるのでは不公平なため、段階的に控除額が減っていき、141万円を超えるとゼロになる仕組みとなっていました。
2018年からこの配偶者特別控除も見直され、妻の年収が「150万円」までは、控除額は減額されないようになります。
150万円を超えると段階的に控除額が減っていき、201万円を超えるとゼロになるようになりました。
また、配偶者控除と同様に、夫の年収(給与収入)が1120万円を超えると控除額が減額され、1220万円を超えると控除額がゼロになります。

※国税庁『平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて(毎月(日)の源泉徴収のしかた)』をもとに編集部作成
つまり、配偶者特別控除の増額と夫の年収制限によって、一般世帯にとっては減税、高所得世帯にとっては増税となったのです。
財務省の試算では、減税となるのはパート主婦世帯を中心に300万世帯強、夫の年収制限を超えて増税になるのは専業主婦世帯を中心に約100万世帯となっています。
今回の税制改正によって、パート主婦はより働きやすくなったといえるでしょう。

しかし、実際には企業の“配偶者手当て”や“家族手当て”の支給条件が、配偶者控除の条件と同じ103万円以下のままとなる可能性が高いという問題があります。
ここも150万円に見直されないと、世帯年収で考えた場合は働き損になる可能性もあるのです。
今回の見直しによる影響は?
ここからは、みなさんから多く寄せられた疑問について紹介します。
Q:社会保険の壁はどうなるの?

今まで、パート主婦には103万円の壁以外にも、社会保険に関係する106万円・130万円の壁がありました。
2018年から103万円の壁は150万円の壁になりますが、106万円の壁・130万円の壁はどうなるのでしょうか?
まず、106万円の壁というのは、2016年10月の改正によって厚生年金と健康保険の加入基準が変わったため新しく誕生した壁です。
一定の要件を満たした場合、年収106万円を超えると妻本人が社会保険に加入しなければなりません。
一定の要件とは…
● 勤務時間が週20時間以上
● 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
● 勤務時間が1年以上見込まれること
● 勤務先の従業員が501人以上であること
となっています。
上記4つの要件をすべて満たした場合、厚生年金と健康保険に加入することになり、“自分”で健康保険料・厚生年金保険料を負担しなければならないのです。※学生は適用除外

そして、年収が130万円を超えると、健康保険の扶養や国民年金の第3号から外れ、保険料や年金を負担することになります。これが130万円の壁です。
いずれの場合も、妻の年収は増えたのに社会保険料負担が増えるため、家計全体で見れば手取りが減ってしまうのです。
結論:2018年からどう働けばいいの?

最後に、妻の年収ごとに世帯収入にどんな影響があるかをまとめてみます。
(夫の年収1220万円以下で試算)
◆年収103万円以下の場合
年収100万円以下の場合は、収入分だけ世帯年収も増加します。
100万円を超えると住民税がかかりますが、数千円ですので大きな影響はありません(100万円以下でも住民税がかかる自治体もあり)。
◆年収103万円超~130万円以下(年収106万円以下の場合あり)の場合
年収103万円を超えると所得税の対象になりますが、年収に応じて段階的に課税されるため、いきなり大きな負担になることはありません。
そのため、働いた分だけ世帯年収も増加します。
ただし、上で紹介した106万円の壁に該当する場合、社会保険料の負担が重くなります(詳細は下記参照)。
◆年収130万円超~150万円以下の場合
年収130万円(条件を満たすと106万円)を超えると夫の社会保険の扶養から外れ、社会保険料を負担しなければなりません。
会社の健康保険と厚生年金に加入できたと仮定すると、年収の15%前後の社会保険料負担となりますので、概算で20万円超の負担となります。
つまり、年収130万円を超えた途端、手取りは110万円をきってしまうのです。
もし、会社で健康保険と厚生年金に加入できない場合、国民健康保険と国民年金に加入することになるため、会社の補助がなくなりさらに負担は増大します。
◆年収150万円超の場合
年収150万円を超えると、収入に応じて配偶者特別控除の金額が段階的に減少していきます。
また、社会保険料の負担があるのは130万円超と同じですので、これを考慮すると、概算で年収160万円までは手取りが130万円以下になってしまいます。
つまり、年収130万円~160万円のゾーンが一番働き損となりますので、130万円を超える場合は160万円を超えることを目指しましょう。
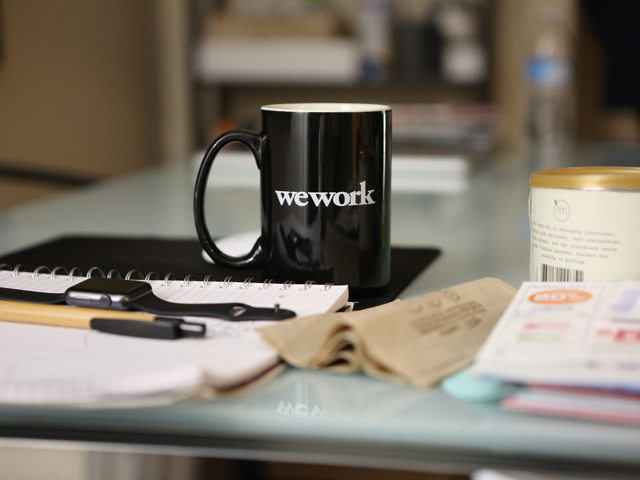
いかがでしたか?
今回の改正で、103万円の壁が150万円の壁になりましたが、社会保険料の壁が変更されていないため、実際に注意すべきなのは社会保険料のふたつの壁(106万円と130万円)であることに変わりはありません。
ただし、妻が厚生年金に加入すれば将来の年金受給額が増えるなどメリットもありますし、そもそも働くことの価値はお金だけではないでしょう。
働き損を回避するか、好きなように働くか、非常に悩ましいところですが、ご自身が一番納得のいく働き方をするのがベストな選択ではないでしょうか。
※2017年11月24日時点の法令にもとづいて執筆しています。また、計算はすべて概算で、お住いの自治体、家族構成、社会保険の種類などによって金額は変わります。
【ライター】
小日向 淳(フリー編集・ライター)
家計の節約術から資産運用、老後資金、相続対策などを中心に構成から執筆までを手がける。『法改正対応 バッチリ相続まるわかり 2015-16年版』(学研マーケティング)/『これで安心! 月5000円からはじめる老後資金の作り方』(宝島社)/『親の入院・介護で困らない!)』(宝島社)ほか、書籍、雑誌、ムック、Web記事など多数。
【参考】
ママニティ