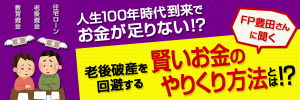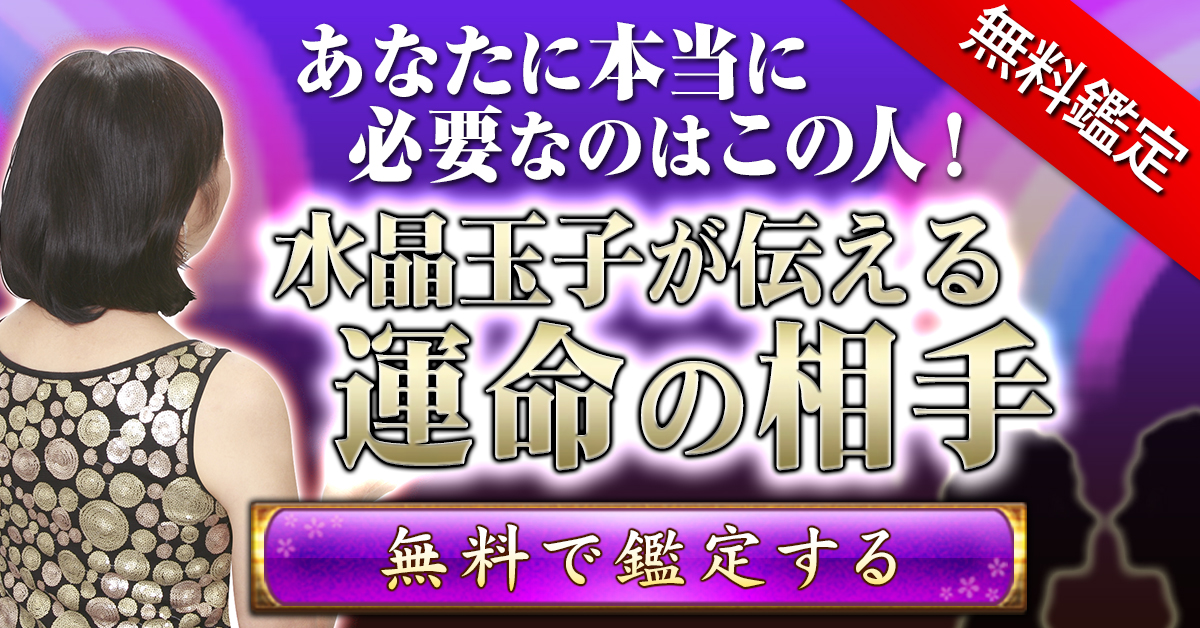病気やケガの治療はなにかとお金がかかるもの。重い病気や大きなケガ、長期の入院となればなおさらです。
万が一の出費に備えて医療保険に入っている方も多いと思いますが、医療費に対しては税額控除や給付金がもらえる公的な制度があるのです。
ただし、これらは情報が少なく、基本的に自分で申請しないと受け取れないため、申請すればもらえるお金を逃してしまっている方が少なくありません。
そこで今回は、病気やケガのとき、知っておきたい控除や補助金についてお伝えします。
医療費控除を忘れずに!

1年間に医療費が10万円以上かかった場合、所得からその分を差し引き、税金を軽減してくれるのが「医療費控除」です。
これは知名度の高い制度ですので、「それは知ってる!」という方が多いのではないでしょうか?
しかし、控除の対象となるものについては、意外なほど知られていません。
医療費控除の対象は、病院の医療費と処方箋による薬代だけだと考えている方が多いようですが、市販の風邪薬や胃腸薬、治療のためのマッサージ、鍼灸代、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、レーシック手術費用、ED治療費用、インプラントの費用、入れ歯の購入費、禁煙治療のほか、通院時の電車代やバス代も対象となるのです。

10万円以上の医療費と聞くと、自分は関係ないと考えてしまいがちですが、上記のものも含めて計算すると意外と超えているものです。一度、家計簿をチェックしてみましょう。
医療費控除を受けるためには「確定申告」が必要です。医療費10万円を超えた方はかならず3月15日までに申告を行ってください。
高額な医療費は医療保険

大きな病気やケガで入院をすると、医療費が高額になることがあります。
そうした場合に備えて、民間の医療保険に入っている方も多いと思いますが、公的医療保険でも高額医療費の負担を軽減する「高額療養費制度」というものがあります。
これは、1カ月(1日から末日まで)の医療費が一定額を超えた場合、超えた部分が払い戻される制度で、年齡が70歳以上か69歳未満か、年収はどれくらいかで上限金額が変わってきます。

概算ですが、70歳未満・年収約370万円~約770万円の人の場合、自己負担額は約9万円弱となります。
仮に大きな病気で入院し1カ月で治療費が100万円かかった場合、本来なら30万円の負担(自己負担3割)になります。しかし、高額医療費制度によって21万円強が給付されるのです。
高額医療費制度は、加入している公的医療保険に「高額療養費の支給申請書」を提出または郵送することで支給が受けられます。
対象の金額になると自動的に高額療養費分を振り込んでくれることもあるようですが、基本的には自分で申請しなければなりません。

高額療養費の支給を受ける権利は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。
もし、過去2年以内に高額な医療負担があった方は、要件を確認して満たすようであれば申請しましょう。
また、70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法もあります。
こちらも手続きが必要ですが、病院に支払う金額が高額療養費制度の自己負担限度額までに抑えられるので、利用できる場合は利用することをおすすめします。
これらの制度の詳しい情報は下記のサイトで確認してください。
→「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(厚生労働省)
→「医療費が高額になりそうなとき」(全国健康保険協会)
病気やケガで障害が残ったら…

もし、病気や怪我で生活や仕事が制限されるような障害が残ってしまったら、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求できます。
障害と聞くと四肢の不自由や失明・失聴などをイメージする方が多いと思いますが、対象となるのはそうした外部障害だけではありません。
統合失調症・うつ病・認知障害・てんかん・知的障害・発達障害などの精神障害、呼吸器疾患・心疾患・腎疾患・肝疾患・血液・造血器疾患・糖尿病などの内部障害も対象となります。
ただし、これらの病気にかかったら即対象となるわけではなく、法令により定められた障害等級表によって状態が判定され、支給の対象となるかどうかが決まります。
支給金額は、年額779,300円が基本で、障害の等級が重い場合1.25倍されます。
また、18歳未満の子ども、または20歳未満の障害者を扶養している場合、第1子・第2子は224,300円、第3子以降は74,800円が加算されます。
障害者年金を受け取るには、「診断書」「病歴・就労状況等申立書」とともに「年金申請書」を提出しなければなりません。障害者年金は存在を知らずに申請を逃している方が多くいるようですので、覚えておいてください。
これらの制度の詳しい情報は下記のサイトで確認してください。
→「障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」(厚生労働省)
→「障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」(日本年金機構)
葬儀にも給付制度あり!

病気や怪我に関する給付制度以外でも、もらえる人は多いにも関わらず、知られていないものがあります。
たとえば、健康保険の加入者が死亡した場合は家族に「埋葬料」として5万円、加入者の家族が亡くなった場合は、加入者に「家族埋葬料」として5万円が、家族がいない場合は実際に葬儀を行った人に「埋葬費」として実費(最大5万円)が支給されます。
これも「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を提出しなければもらえないため、多くの人が受け取らないままとなっているようです。
いかがでしたか?
国や公的機関の制度は、説明が難解なことが多く、自治体独自のものなどもあるためわかりにくいのですが、「妊娠や出産に関するもの」「介護に関するもの」など、今回紹介しきれなかったものがたくさんあります。
一度、お住いの自治体の補助金や給付金制度などをいろいろと調べてみてください。思わぬものが見つかるかもしれません。
※こちらの記事は2018年1月の執筆時点のものであり、正確性を保証するものではありません。 正しい情報、最新の情報についてはご自身でご確認ください。
【ライター】小日向 淳(フリー編集・ライター)
家計の節約術から資産運用、老後資金、相続対策などを中心に構成から執筆までを手がける。
『法改正対応 バッチリ相続まるわかり 2015-16年版』(学研マーケティング)/『これで安心! 月5000円からはじめる老後資金の作り方』(宝島社)/『親の入院・介護で困らない!)』(宝島社)ほか、書籍、雑誌、ムック、Web記事など多数。