
子供達のトラブルは、時代と共に変化しています。
昔は、トラブル内容も複雑ではなく、お友達同士のちょっとした喧嘩や、子供同士がぶつかってどちらかが怪我をしてしまった、など単純なものが多く、いじめや仲間外れは担任の先生から見えていました。
先生も気づけば注意したし、子供達も先生の言うことはきちんと聞いていました。
一方、現代の子供同士のトラブルは、解決が難しくなったのではないでしょうか。
子供たちの間でどんなトラブルがあり、どのように対応すればよいのか。
今回は家族問題カウンセラーの山脇由貴子さんに話を伺いました。
小学生のトラブルは時代とともに変化している
インターネットとゲームがもたらす影響とは
不登校の理解の変化
小学校低学年でのトラブル~友達ができない~
お友達同士での金銭、物の貸し借りでのトラブルも……
小学校低学年のトラブル解決で大事なのはお母さん同士の関係
中学年高学年でのトラブル~普通級、特別支援学級どっち?~
年齢を重ねるごとに子供のいじめも深刻に……
オンラインゲームもトラブルの要因に
様々なトラブルに立ち向かうための親として心がまえとは?
1.「自分で出来る子」に育てる
2.子供へのプライベートゾーン教育
3.先生とのコミュニケーションは細やかに
4.長期休みの過ごし方に注意
小学生のトラブルは時代とともに変化している

例えば、仲の良いお友達同士がその日喧嘩をして、一方が怪我をしたとします。
以前なら、先生が間に入って、けがをさせてしまった子に謝らせ、じゃあこれで仲直り、と出来ていました。
ですが今は、ちょっとした怪我でも、親同士の面識がないと、治療費を請求されたりします。学校も管理責任を問われます。
病院に行くためのタクシー代を請求された、というお母さんもいます。
インターネットとゲームがもたらす影響とは

インターネットと携帯電話の影響により、子供達のいじめはとても見えにくくなりました。
現代の子供同士のいじめは携帯を使うのは当然のことです。
「死ね」などの言葉をメールで送られて来たり、ラインで悪口送られたり。そしてグループラインでのライン外しも、いじめの主流となっている、と言ってよいでしょう。
先生や親の知らない所でいじめが進行してしまうのです。
お母さん達も、ママ友のラインが始まると付き合わない訳に行かず、料理中も、食事中もずっと携帯をチェックしている、本当はグループラインはしたくないのに……。
ランチに誘われて、3,000円のランチは無理なんだけど、断れなくて、というお母さんもいます。
また、子供同士がオンラインのゲームをするようになり、ゲームが原因のトラブルも増えて来ています。
子供が夜中までゲームをするので、朝起きられずに遅刻するようになってしまった。そんな悩みを抱えているお母さんは増え続けています。
不登校の理解の変化

不登校については、学校は厳しくなりました。今は、子供が7日間連続して学校を休むと、学校は教育委員会に通報しなくてはいけないことになっています。
理由は、虐待されているかもしれないから、です。
子供が1週間学校を休んだら、親は虐待を疑われるのです。
そして、地域によりますが、子供がどんなに嫌がっても、無理やりにでも学校に連れて来るように言われ、困っているお母さんもいます。
いじめを中心に、幼稚園、学校で起こるトラブルを先生達も解決できずに困っているのが現状です。
だから、学校に任せておくだけではトラブルは解決されません。これからは、子供達のトラブルを解決には、お母さん達の力がますます重要になってきています。
小学校低学年でのトラブル~友達ができない~

小学校に入って、なかなかお友達が出来ない。そんなお悩みも多いです。
小学校というのは、子供にとっては、幼稚園や保育園とのギャップがとても大きいのです。
今までは、ずっと先生がそばにいてくれたけれど、急に全部自分でやらなくてはいけなくなります。
遊びも、先生が決めてくれていたので、仲間に入れないなんてことはなかったけれど、遊びに入れてもらうにも自分から声をかけなくてはなりません。
なんて言って仲間に入れてもらえばいいのかわからない子もたくさんいます。なかなか集団に入れない、お友達が出来ないお子さんは、担任の先生の力を借りることをお勧めします。
お母さんから先生に、お友達を作るのが苦手な事を伝え、配慮してもらうようにしましょう。
また、お家で、お友達に声をかける「練習」をお母さんが一緒にやってあげるのも効果があります。
「緊張しちゃうよね」なんて言いながら、「でも絶対大丈夫!」と励ましながら。
出来なかったとしても「大丈夫、またやってみようね」とまた励まして。
お母さんの支えと、「大丈夫」と言ってもらう事はお子さんの心の支えになります。
お友達同士での金銭、物の貸し借りでのトラブルも……

お友達は出来たけれど、お友達から毎回、お菓子やお金を持って来て、とねだられて子供が困っている。
そんな悩みを持つお母さんもいます。子供のお友達との付き合いに、親はどれだけ口をはさんで良いものなのでしょうか?
そんなご相談もよくあります。
毎回、何かを持ってくるように言われるようになると危険です。
特にお金は金額がエスカレートしてゆきます。中には「お金を持ってこないと遊んであげないよ」と言われて、持ってゆく子もいますが、親としては絶対に止めて下さい。
お子さんは、そのお友達と遊びたい、と言うかもしれませんが、お金を持ってゆかなければ遊んでくれないなんて、お友達とは言えません。
その子と遊んではいけない、と禁止するのではなく、「お金を使わない遊びをしようね」と言ってあげましょう。
相手の親御さんと連絡が取れれば、直接話をするのも良いことです。
担任の先生にも事情を伝えておいた方が良いでしょう。クラス全体に、そういう事はしないように、と注意してくれるかもしれません。
小学校低学年のトラブル解決で大事なのはお母さん同士の関係

小学校低学年のうちは、お友達の物を壊した、とか叩かれた、叩いた、というトラブルがよく起こる年齢でもあります。
出来る限り、お子さんが一緒に遊ぶお友達の親御さんとは連絡を取り合うようにしておくと、何かトラブルがあった時にもおおごとにならないで済みます。
お母さん同士が知り合いであれば、けがをさせてしまったり、物を壊してしまっても、すぐに謝れば「このくらい、大丈夫」となります。
つまり、お母さん同士が仲が良いことが大切なのです。
お母さん同士の中が悪いと、子供同士の関係もぎすぎすしたものになってしまうのです。
中学年高学年でのトラブル~普通級、特別支援学級どっち?~
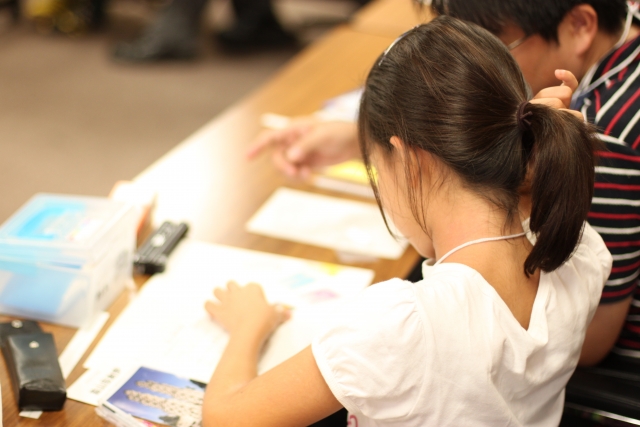
小学校中学年、高学年になると、トラブルの内容がまた変わってきます。
お勉強についてゆけない、授業中落ち着きがない、などの理由で、特別支援学級を勧められた、「うちの子は、発達障害なんですが、いつまで普通学級でやっていって良いのでしょうか?」というご相談はとても多いです。
小学校高学年になると、お勉強もお友達との関係も難しくなってきます。
ですので、高学年になるタイミングで、普通学級と特別支援学級、どちらがお子さんに合っているのかを考えるのは良いと思います。
特別支援学級や情緒障害児学級に抵抗があるお母さんも多いですが、重要なのは、先生から強く勧められた、とか、発達障害だから、という事ではなく、あくまでお子さんにどちらが合っているのか、という事です。
まずは今のクラスが、お子さんの学力レベルに合っているか、が重要です。
授業の内容が全く理解出来ずに座っているだけになっているのなら、お子さんの学力が伸びなくなってしまいます。
そしてお友達とうまく行っていないのであれば、毎日学校で辛い思いをしているかもしれません。
授業の様子やノートを見てあげて、そして最後はお子さん自身がどうしたいか、特別支援学級を見学した上で、お子さんの気持ちを聞いてあげる事が大切です。
お子さんには毎日、楽しく学校に通って欲しいですものね。
年齢を重ねるごとに子供のいじめも深刻に……

小学校高学年になると、いじめも深刻で、かつ陰湿になりがちです。
インターネットを使い、大人から見えないいじめも始まる頃です。いじめを解決するのは保護者と学校が協力し、時間をかけて取り組まなければなりません。
でも何より、お子さんが傷つかないように守ってあげることが一番大切です。
もし、お子さんが学校に行きたくない、と言い始めたり、何か辛いことがある様子だったら、しばらく学校は休ませてあげましょう。
お勉強の事は心配ですが、一番大事なのはお子さんの「心」です。
お子さんが安心出来るまで学校をお休みさせて、何があったのかを自分から話してくれるまで待ってあげましょう。
お母さんは自分の気持ちを大事にしてくれている、と感じればお子さんの方から必ず話してくれます。その話の内容次第で、親御さんが何をしてあげたらいいか、先生に何をしてもらったらよいかが見えて来るはずです。
そして子供達の中でいじめがあるのを見つけたら、放ってはおかず、先生に相談に行くことは必要なことです。
自分の子供がいじめの被害者、あるいは加害者になるのを防ぐためです。
オンラインゲームもトラブルの要因に

ゲームのトラブルも増えて来る年齢です。
お子さんがお友達とオンラインゲームの約束をし、夜遅くまでゲームをしていて、朝なかなか起きられない。
ゲームを早くやめるように言ったら、「でも〇〇くんと約束しているから……」断れずに困っている子もたくさんいます。
大切なのは、お子さんがゲームをしているお友達のお母さんと連絡を取ることです。
子供同士で約束するのではなく、お母さん同士でゲームのルールを決めて、夜8時になったらお母さんが預かる、など出来ると良いですね。
様々なトラブルに立ち向かうための親として心がまえとは?

子育ての中で、親として、どんなことに気を付けたらよいのかをまとめてみましょう。
1.「自分で出来る子」に育てる

まず、子供を大事にし過ぎない、という事は大切です。
お子さんを年齢相応に成長させる為には、少しずつお母さんがやってあげる事を減らしてゆくことが大切です。
心配だから、きちんと出来ないかもしれないから、と、着替えや学校の準備や宿題、なんでもやってあげていると、お子さんは自分1人では何も出来ない子になってしまいます。
お友達とのトラブルも、大人が関わらなくてはならない部分もありますが、自分で謝って仲直り出来る力を育ててあげることも重要です。
2.子供へのプライベートゾーン教育

そして、プライベートゾーンについては早くから教えてあげることも重要です。
触ったり見たりしてはいけない身体の部分を教えておいてあげると、不用意にお友達の大切な部分を触って大きなトラブルになったり、被害に遭ってしまうことを防ぐことが出来ます。
その為には、スキンシップもお子さんの年齢を考えて、減らしてゆくことが大事です。
男の子がいつまでもお母さんのおっぱいを触るのを許していると、外で女の人のおっぱいを触ってもいい、と思ってしまうかもしれません。
女の人の大切な部分であり、触ってはいけないし、年齢的にも「おかしい」こと、をきちんと教えてあげましょう。
3.先生とのコミュニケーションは細やかに

学校の先生とのコミュニケーションは多ければ多いほど良いです。
保護者会や面談の時や、何か困った事があった時に相談するだけでなく、出来る限り日常的にコミュニケーションをとるように心がけましょう。
先生は忙しいから、と遠慮する気持ちも分かりますが、普段からコミュニケーションを取っていれば、ちょっと子供の様子がおかしいな?と思った時に、すぐに先生に学校での様子を聞くことが出来ます。
お子さんがいじめられていると分かった時にも、先生と親御さんがどうすれば解決出来るか、一緒に考えることが出来ます。
4.長期休みの過ごし方に注意

そして長期のお休みです。
最近は、ママ友同士でフェイスブックやインスタグラムをチェックしていたりするので、海外旅行をしてアップしなきゃ、食卓の写真は豪華にしなきゃ、と無理をしているお母さんもたくさんいます。
お金がかかり過ぎて、ご主人に怒られてしまった、という方も。
当然のことですが、無理は続きません。
そして、長期休みはイベント盛りだくさんにする必要はないのです。
お休みが楽し過ぎると、子供は学校に行きたくなくなってしまうかもしれないのです。
お休みの後半は、子供が退屈し、早く学校に行きたい、と思うくらいがちょうどよいのです。
だからお母さん達、無理しないでくださいね!

監修:山脇由貴子(やまわきゆきこ)
女性の生き方アドバイザー
家族問題カウンセラー
東京都内の児童相談所に心理の専門家として19年間勤務。子どもの問題を扱ううちに見えてきた家族の問題、そして女性のあらゆる悩みを解決すべく、個人の心理オフィスを開設。子育てや夫婦関係、仕事や婚活などの悩みを始め、毎日の中の「なんとなく満ち足りない」といった思いの解消まで、幅広くサポート。
新聞、雑誌、TVなど多くのメディアにも出演。日本全国で精力的に講演会も実施。いじめ問題などテーマにした著書も多数。
子育てが辛い、うまくいかない・・・と感じたら気軽に相談を!初回相談は無料。
山脇由貴子心理オフィス














