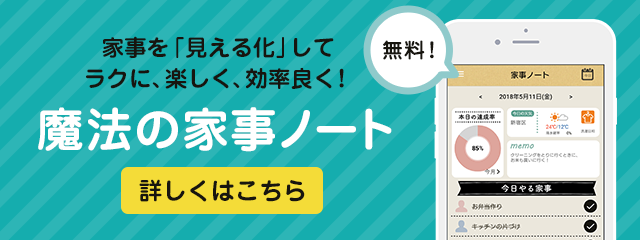現在、健康寿命は「男性が72歳、女性が75歳」とよくいわれますが、実態とはズレがあるようです。

健康食品など、高齢者向けの商品やサービスのCMでは、よく次のように強調しています。
「健康寿命は今、男性が72歳、女性が75歳。一方、平均寿命は男性81歳、女性87歳なので、男性は9年、女性は12年もの間、支援や介護が必要な状態になっています。この期間を短くし、長く自立生活をするために、○○を習慣にして健康寿命を延ばしましょう」
厚労省調査と現実の乖離
このメッセージに違和感を持つ人はあまりいないようですが、身の回りを見渡してみれば、70代前半の人のほとんどは支援を受けず、自立して生活していることが分かるはずです。
厚生労働省発表の2017年度「介護給付費等実態調査の概況」では、介護予防サービスや介護サービスを1年間継続して受給した人は、70代前半で男女とも4%台前半という、とても低い数値となっています。つまり、「70代前半で健康寿命が尽きる」というのは、実感でもデータにおいても疑問符がつきます。なぜ、このような乖離(かいり)が起こるのでしょうか。
健康寿命は「健康上の問題で、日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されています。そして、健康寿命は国民生活基礎調査において「あなたは現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」「あなたの現在の健康状態はいかがですか」という質問を行い、「日常生活に制限のない期間の平均」「自分が健康であると自覚している期間の平均」を算出し、年代別人口や生存率などを加味して導かれています。
ということは、要介護認定とは何の関係もなく、回答者の主観に基づいた数値なのです。例えば、「どこか体が痛くて動きにくい」「何となく病気がちで体調がよくない」という人もかなり含まれるでしょうし、調査対象は高齢者だけではないので、若くして障害や難病を抱えた人たち、健康なのにたまたま調査時にけがや病気をしていた人たちも含まれる可能性があります。
もちろん、「健康上の問題で、日常生活が制限されることなく生活できる期間」という定義からして、この算出方法がおかしいとはいえませんが、実感やデータから見て、「男性72歳、女性75歳」という健康寿命が若過ぎるのは、このような調査方法を採っている結果だということです。
65歳男性は82.2歳、女性は85.5歳?
一般には、健康寿命を「高齢者が自立を失って、要介護状態になる平均的な年齢」といった捉え方をしている人が多いでしょう。実際、先述のCMのようなメッセージでは、健康寿命をそのような意味で使っています。
実は、このような捉え方に合った「健康寿命」が分かる調査結果があります。2012年に発表された「健康寿命の算定方法の指針」という論文です。これは、大学教授などでつくる「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班」がまとめたもので、この中に、65歳の人が死亡するまでの間、自立して(『要介護認定2』以上を受けずに)生活している期間と自立していない(『要介護認定2』以上になった)期間について、男女別の年次推移があります。
これによると、2010年時点で、65歳の男性の平均余命は18.9年。そのうち、自立生活期間が17.2年、自立していない期間が1.6年でした。65歳女性の平均余命は24.0年で、自立生活期間が20.5年、自立していない期間が3.4年です。
つまり、一般に認識されている「自立生活ができる(要介護状態ではない)」という意味での「健康寿命」は、2010年時点で65歳男性が82.2歳(65歳+17.2年)、同じく、女性が85.5歳(65歳+20.5年)で、介護が必要な期間は平均で男性1.6年、女性で3.4年にすぎないということです。
私はそもそも、「『ゼロ歳児が平均的に何歳まで生きそうか』という推定値」である平均寿命と、「全年代に対するアンケートによる主観的健康度」である健康寿命との差を出し、高齢者に対して「9~12年の期間の健康維持に努めましょう」というのは、やや強引だと考えています。
CMなどを通して「70代前半で健康寿命が尽き、10年間も要介護状態になるかもしれない」といった認識が広まれば、高齢者や高齢期を迎える人たちが老いを恐れ、身体的健康維持のことばかり考えるような萎縮を生むのではと危惧します。
今、私たちが共有すべきは、65歳で健康な人の「健康寿命」は男性が82歳、女性は85歳であるという事実です。また、その年齢を超えても、85~89歳で介護給付を受けている人の割合は男性は30%弱にすぎず、女性もおよそ45%です(2017年度「介護給付費等実態調査の概況」)。
65歳で健康ならその後、平均して20年程度の自立生活期間があります。そう考えれば、大切なのは「健康寿命を延ばす」ことより、「平均でも約20年ある健康な高齢期を、どのようにして有意義に楽しく暮らすか」であるはずです。
(NPO法人・老いの工学研究所 理事長 川口雅裕)
川口雅裕(かわぐち・まさひろ)
NPO法人「老いの工学研究所」理事長
1964年生まれ。京都大学教育学部卒。リクルートグループで人事部門を中心にキャリアを積む。退社後、2012年より高齢者・高齢社会に関する研究活動を開始。高齢社会に関する講演や執筆活動を行うほか、新聞・テレビなどのメディアにも多数取り上げられている。著書に「だから社員が育たない」(労働調査会)、「チームづくりのマネジメント再入門」(メディカ出版)、「速習! 看護管理者のためのフレームワーク思考53」(メディカ出版)、「なりたい老人になろう~65歳から楽しい年のとり方」(Kindle版)など。老いの工学研究所(http://oikohken.or.jp/)。