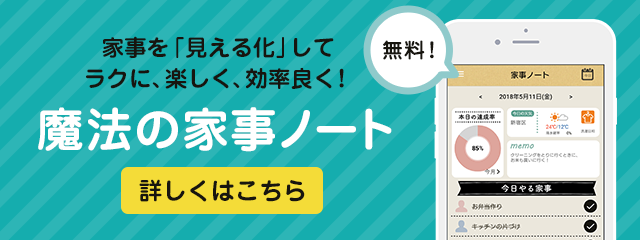料理に欠かせない「小麦粉」と「片栗粉」。いずれも、揚げ物の衣やとろみづけに使用するほか、肉や魚にまぶしてソテーするなど、その用途は多岐にわたります。しかし便利に使える半面、どちらを使うべきか迷ってしまうことも多いはず。小麦粉と片栗粉はどのように使い分けるのがよいのでしょうか。
オトナンサー編集部では、「エコール 辻 東京」(辻調グループ)食品衛生教育研究グループの迫井千晶さんに聞きました。
小麦粉=柔らかい粘り、片栗粉=強いとろみ
そもそも、小麦粉の原料は小麦、片栗粉はジャガイモに含まれるデンプンです。小麦をそのままひいて粉にする小麦粉は「風味」があるのに対し、無味無臭のデンプンから作られる片栗粉は風味がありません。「小麦粉に含まれるタンパク質は水を加えるとグルテンを形成し柔らかい粘りを生みます。片栗粉は水に溶けにくい性質がありますが、加熱により少量でも強いとろみを出せます」(迫井さん)。
その成分が異なることから、料理の仕上がりにも違いが生まれます。それぞれの特徴を知ることが、両者を使い分ける上でのポイントです。
【とろみをつける料理】
透明感のあるとろみが欲しい料理は片栗粉。小麦粉よりも低い温度でとろみが出るため、中華料理のあんかけやかき卵汁などに適します。「片栗粉のデンプンは加熱により糊化(こか)する性質があり、調理中の熱い料理に粉のまま加えるとすぐダマになってしまいます。必ず水に溶いてから使いましょう」。一方、小麦粉は透明度が少なく粘度が弱いのが特徴で、シチューやカレーなどの煮込み料理に最適です。
【揚げ物の衣】
揚げ物の衣は使用する粉によって食感が変わります。鶏の唐揚げの場合、小麦粉を使うと表面がカリッとしたきつね色に、片栗粉を使うと表面は白っぽく、サクサクとした軽い食感に揚がります。揚げ出し豆腐には、だし汁をかけた時に絡みやすいもっちりとした衣になる片栗粉、酢豚の肉には、あんをかけた後もベタつかず、表面のカリッとした食感をキープしやすい小麦粉が最適。「好みの食感や料理に合わせて使い分けることはもちろん、小麦粉と片栗粉をミックスして使うのもよいでしょう」。
小麦粉は肉や魚をジューシーに
【炒め物・ソテー】
肉や魚、野菜を炒めたり、ソテーしたりする前に粉をまぶす工程は、レシピ本によっては使用する粉が異なる場合がありますが、「肉や魚を香ばしくジューシーに焼きたい場合は小麦粉。表面に水気を帯びたものに付きやすいためムニエルの衣などにも使われます」。小麦粉はタンパク質を含んで焦げやすく、火加減に注意が必要です。
一方、調理の最後に合わせ調味料を加えることが多い中華の炒め物には、片栗粉が多く用いられます。「肉や魚介類に片栗粉をまぶしてから炒めることで、調味料が絡みやすくなるのです。また、表面がコーティングされ強火で炒めても水分が逃げず、柔らかさを保てます」。
【その他の料理】
南蛮漬けや照り焼きなどの場合、肉や魚に小麦粉をつけるとタレに程良いとろみが生まれ、さっぱりと仕上がります。
(オトナンサー編集部)