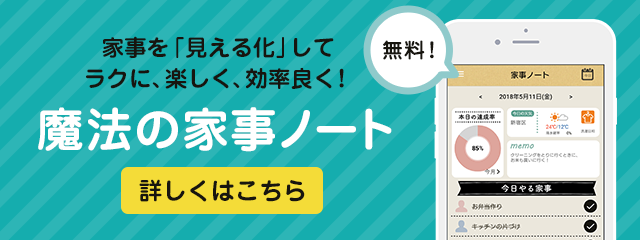「ワンワン(犬)きた」「ブーブ(車)乗りたい」「マンマ(ご飯)食べる」。少しずつ言葉を発するようになった子どもが話す、かわいい「幼児語」。親や周囲の大人も、つい一緒になって使ってしまうものですが、ネット上では「言い直させた方がよいのかな」「どう会話するべきか迷う」「正しい日本語を覚えるのが遅くなったらどうしよう」などの声が上がっており、悩む親も多いようです。
幼児語を話し始めたわが子とのコミュニケーションや、正しい言葉を教える方法とは、どのようなものでしょうか。20年間にわたって学習塾を経営し、著書に「1人でできる子になる テキトー母さん流 子育てのコツ」(日本実業出版社)などがある、子育て本著者・講演家の立石美津子さんにお話を伺いました。
対応誤ると「卒業」できない場合も
「ワンワン」「マンマ」など、子どもが話す「幼児語」は幼い声も相まって、とてもかわいいです。子どもに合わせて「マンマ食べようね」などと声をかける親も多いでしょう。
しかし、かわいいからといって周囲の大人がずっと幼児語を使っていると、子どもが自分で話す言葉と、耳に入る親の言葉が同じままになり、いつまでたっても幼児語を卒業できなくなってしまう可能性があります。
そもそも、子どもが幼児語を発するのは、顎や舌、歯などの発達が未熟で上手に発音するのが難しく、「ご飯」よりも「マンマ」、「犬」よりも「ワンワン」の方が言いやすいからです。
ですから、子どもの幼児語を禁止する必要はありません。子どもが幼児語を発するたびに、「ワンワンじゃなくて『犬』でしょ!」と叱ったり、「犬」と言えるまで言い直しを繰り返させたりすると、子どもは「言葉を発すること」に不安を感じ、おしゃべりをしなくなってしまいます。
幼児期に大切なのは、子どもが自ら進んで多くの言葉を発することです。それに対して、親や周囲の大人ができるだけ多くの言葉を返し、「言葉のシャワー」を浴びせてあげることで、語彙(ごい)力がどんどん育っていきます。子どもの幼児語を封じ込めるのではなく、積極的に発することができる環境づくりを心掛けましょう。
「正しい日本語の環境」を与える
幼児語の多用を控えた方がよいのは、子どもではなく大人です。子どもが日頃から正しい日本語を耳にしていれば、言葉遣いがおのずと軌道修正され、幼児語から卒業できるようになります。親が意識すべきなのは、幼児語の言い直しではなく、正しい日本語の環境を与えることです。
例えば、おもちゃを片付ける場面で、子どもが「ないないする」と言ったとき、「そうね、お片付けしようね」と返していると、子どもは「お片付けする」と言うようになります。子どもが「マンマおいちい」と言ったときは、「おいちいね」ではなく、「おいしいね」と返して正しい日本語を聞かせれば、舌や筋肉の発達とともに自然と軌道修正され、やがて、幼児語から卒業できます。
同様に、日付の読み方も子どもには難しく感じられるかもしれません。小学5~6年生になっても、「1日」を「いちにち」、「8日」を「はちにち」、「20日」を「にじゅうにち」と読む子どもも実際にいます。しかし、家庭生活の中でカレンダーを見ながら「今日はさんがつついたち(3月1日)ね」と親と会話をしている子どもは、小学校入学前に正しい日付の読み方を自然と習得しているケースが多いのです。
一度インプットしたことを、後から修正して覚え直すのは大変な作業です。「子どもだから難しいだろう」「まだ時期的に早いのでは」と判断し、社会では使われない言い方をずっと使わせていると、後から苦労するのは子ども自身です。
親や周囲の大人が正しい日本語で会話することを日常的に意識していれば、特に教えなくとも、子どもは持ち前の吸収力でどんどん覚え、自然と正しい言葉を身につけていくでしょう。
(文/構成・オトナンサー編集部)
立石美津子(たていし・みつこ)
子育て本著者・講演家
20年間学習塾を経営。現在は著者・講演家として活動。著書は「1人でできる子が育つ テキトー母さんのすすめ」「はずれ先生にあたったとき読む本」「子どもも親も幸せになる 発達障害の子の育て方」など多数。ノンフィクション「発達障害に生まれて 自閉症児と母の17年」(小児外科医・松永正訓著)のモデルにもなっている。オフィシャルブログ(http://www.tateishi-mitsuko.com/blog/)。