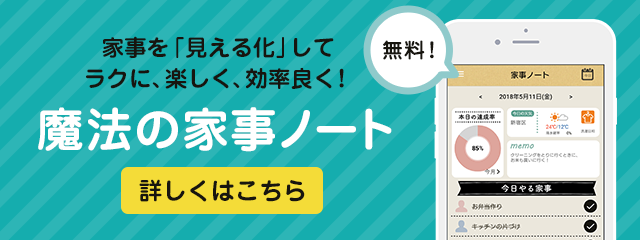ご飯茶わんでお茶を飲むのは是か非か、ネット上で議論になっています。専門家に聞きました。

「ご飯を食べ終わった後、ご飯茶わんに麦茶を注いで飲んだら『お茶漬けでもないのに下品』と言われた」
このような内容の投稿が先日、ネット上で話題になりました。ご飯茶わんでお茶を飲む行為について、「洗い物の負担が減る」「禅寺では正しい作法」など肯定的な声がある一方、「下品だと思う」など否定的な意見もあります。「『茶わん』だから、お茶を飲むのが本来の使い方では」との声も。
専門家の見解とは、どのようなものでしょうか。和文化研究家で日本礼法教授の齊木由香さんに聞きました。
水が貴重な時代の習慣
Q.そもそも、茶わんでご飯を食べるという習慣はいつごろ始まったのでしょうか。
齊木さん「茶わんでご飯を食べるようになったのは、江戸時代に入ってからです。それまで、一般庶民の間では、飯や汁をいただくために木製の『わん』が使われていました。江戸時代に国産の磁器が作られるようになり、茶わんはお茶を飲むための器から、ご飯をいただく食器へと用途が広がっていきました」
Q.なぜ、ご飯を食べる器なのに「茶わん」と呼ぶのでしょうか。
齊木さん「茶わんは本来、お茶を飲むときに用いられる器のことで、それがご飯を盛る器にも使われるようになったことから『お茶わん』と呼ばれるようになりました。
そもそも、茶わんは平安時代、禅僧が中国から仏器として持ち帰ったのが最初とされています。鎌倉時代に入って僧侶を中心として茶道が広まり、茶わんがもてはやされるようになりましたが、当時はごく上流階級の人たちに限られていました。
もともとは茶道のための茶わんでしたが、室町時代になると磁器の代名詞として呼ばれるようになりました。当時、中国から磁器を輸入しており、花瓶・皿・鉢などがある中で茶わんが一番多かったことから、磁器そのものを『茶わん』と呼んだのです。
そして、お茶を飲むための茶わんを『抹茶(煎茶)茶わん』、ご飯用のものを『ご飯茶わん』と区別し、中でも、主食であるご飯は使用頻度が高かったことから、単に『お茶わん』と呼ばれるようになりました」
Q.ご飯を食べ終わった後、茶わんでお茶を飲むのは作法として正しいのでしょうか。
齊木さん「ご飯を食べ終わった後の茶わんでお茶を飲むのは、昔は正しいとされていました。昔、水が貴重な時代は毎回食器を洗うわけにはいきませんでした。茶わんについたご飯粒を漬物でなで取り、洗わずにしまっていました。食料が貴重だった時代においても同様で、生活の知恵ともいえそうです。
しかし、現在、ご飯を食べ終わった後の茶わんでお茶を飲むのはNGです。なぜなら、現代においては『湯飲み茶わん』という器があるからです。ご飯をよそっていない茶わんで飲む場合も同様です。
ただし、自分一人で食べる場合や、家庭において昔の風習が残っている場合は構いません。食事では、周りに不快な思いをさせないことが基本です。『湯飲み茶わん』『ご飯茶わん』など、さまざまな器が普及している現代においては不作法にあたるので、外食では控えた方が無難です」
禅寺では今も正しい作法
Q.ご飯を食べ終わった後の茶わんでお茶を飲むことが、禅寺では正しい、というのは事実でしょうか。
齊木さん「事実です。修行僧にとってお食事をいただくことは、命をつなぐ大切なものとされており、『絶対に残さない』などの心得があります。お茶わんでお茶を飲むことでいうと、沢庵(たくあん)を1枚残しておきます。食事の最後にお茶を入れてお茶わんに残ったご飯粒をこそげ落として、きれいに洗います。そして最後に全ていただくのが作法とされています」
Q.お茶漬けは作法的に正しいものなのでしょうか。
齊木さん「お茶漬けは、日本古来のお米の食べ方であり、伝統的食事法という観点からすると正しいといえます。ただ、ここで気を付けなければならないのは、『箸の使い方』です。箸先は3センチ以上濡らすと不作法になります。つまり、お茶漬けをいただく際には、箸先はお茶につけず、わんからササっとすするのが作法とされています。『鯛(たい)茶漬け』『ひつまぶし』などの料理として出される場合も、いただき方に注意して味わってみてはいかがでしょうか」
Q.茶わんと湯飲みの正しい使い分け方など、ご飯とお茶に関する正しい作法があれば教えてください。
齊木さん「『茶わん』という場合は『飯茶わん』を示すことが多く、ご飯をよそうための『わん』は、特に『ご飯茶わん』『飯わん』と呼んで区別しますが、一般的にご飯をよそうものです。一方、『湯飲み』は飲み物を飲むときに使う器を指します。『湯飲み茶わん』ともいい、お茶やお湯など熱いものを注ぐことに適します。
ご飯やお茶をいただく際には作法があります。ご飯は、茶わんを左手(利き手ではない方。左利きの人は逆)に持ち、お箸の箸先3センチ以内を使い、少量ずつすくい上げて口に運びます。また、ご飯は手前から奥へ向かって食べると、きれいにいただけます。お茶は、湯飲み茶わんの絵柄を正面に出されたら、気持ち正面を外して飲むのが粋とされています。
また、湯のみ茶わんに取っ手がないのは、お湯の温度を確かめ、適温で飲む(お出しする)ため。日本人の心遣いともいえそうです」
(オトナンサー編集部)
齊木由香(さいき・ゆか)
日本礼法教授、和文化研究家、着付師
旧酒蔵家出身で、幼少期から「新年のあいさつ」などの年間行事で和装を着用し、着物に親しむ。大妻女子大学で着物を生地から製作するなど、日本文化における衣食住について研究。2002年に芸能プロダクションによる約4000人のオーディションを勝ち抜き、テレビドラマやCM、映画などに多数出演。ドラマで和装を着用した経験を生かし“魅せる着物”を提案する。保有資格は「民族衣装文化普及協会認定着物着付師範」「日本礼法教授」「食生活アドバイザー」「秘書検定1級」「英語検定2級」など。オフィシャルブログ(http://ameblo.jp/yukasaiki)。