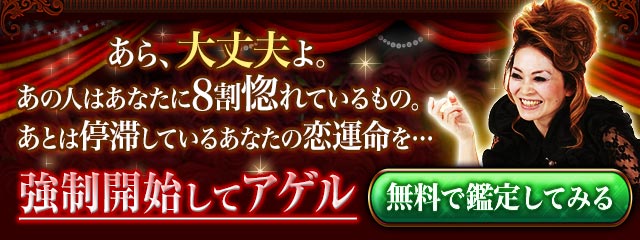我が家には、おもちゃが溢れています。
私が買うわけでもないのに、おもちゃが増えていきます。
理由は、両親と義両親。双方の親からのプレゼントなのです。
いつでも買って貰えるこの環境。
そんな子どもに成長していくのではないかと、私はビクビクしています。
豊かさが物を大切にする心を奪っている?

物を大切にする親であっても、大切に出来ない子どもがいます。
冒頭にも書きましたが、今の子どもは、
-
おじいちゃん
-
おばあちゃん
-
両親
など、財布をたくさん持っています。
つまり、「誰かにお願いすれば買ってくれる」ことが普通になっているのです。
また、物が溢れていると、物がどこにあるのか分からなくなります。
お片付けが上手くできないとなると行方不明になることも。
こんな状態を繰り返していると物を大切にする心は育ちません。
「おかえりなさい」お片付けが効く!

子どもだけではありません。
お片付けが苦手なママ、いませんか?
実は、私も片付けが苦手です。
しかし、「おかえりなさい」お片付けを実践するようになってから劇的に変わりました。
「おかえりなさい」つまり物の定位置を決めたのです。

子ども達にも「物にも帰るおうちがあるんだよ」と話します。
そして親子一緒に物の帰るおうちを決めます。
「ここはおもちゃさんのお家」
「ここは帽子さんのお家」
話をしながら、そこにシールなどで表札をつけていきます。
これだけで子ども達の中で物語ができ上がり、自然とお片付けをするようになります。
「おもちゃを片付けないなら捨てるよ!」と言って片付けを促す方法もあるようですが、物を大切にするという考え方とはズレているので、私はオススメしません。
失くした体験から物の大切さを学べるのは小学生に入るまでと言われています。
失くしても買ってもらえる、どうにかしてもらえると思うような子どもにはなって欲しくないですよね。
親子で一緒に考えて根気強く子どもの意識を変えていくことが大事なのかもしれません。
二児のママ。子育て応援ZEROSAI代表。
長男の出産をきっかけに、子育て支援をはじめ、高知県内外各地で子育てイベントを開催しています。
その中で、いかに、育児と家事を楽しむか、息を抜くか、手を抜くか(笑)毎日奮闘しています。
子育て応援「ZEROSAI」