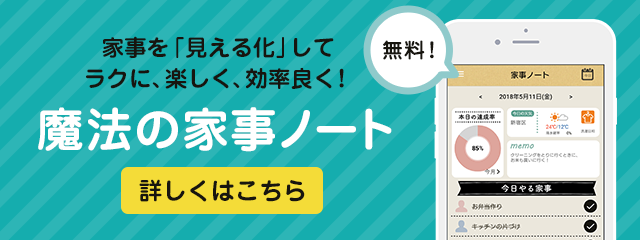春は家族で出かけることが増える時期。子ども連れの旅行や帰省の移動手段として「新幹線」を使う人も多いと思います。しかし、利用客が大勢いる上に長時間乗車する新幹線では、ぐずったり騒いだりする子どもも多く、親にとっては悩みのタネです。ネット上でも「後ろの席の子どもに、いすを蹴(け)られたことがある」「子どもが泣くのは仕方ないけどそれを放置している親は腹が立ちます」「子どもが騒ぎ出したら、せめてデッキに行くべきだ」など、さまざまな声が上がっています。
子ども連れで新幹線に乗る際、意識すべき振る舞いとはどのようなものでしょうか。著書に「1人でできる子になる テキトー母さん流 子育てのコツ」(日本実業出版社)などがある、子育て本著者・講演家の立石美津子さんに聞きました。
「遠足前の先生」をイメージする
Q.車内で気を付けるべきマナーとは、どのようなものでしょうか。
立石さん「新幹線は在来線とは異なり、長時間乗車します。子どもにとっては、1~2時間以上いすに座っておとなしく過ごすのは退屈であり、じっとしていることに飽きてしまう子もいるでしょう。通路をウロウロしたり、いすの上に立って遊んだりして、他の乗客の迷惑にならないように注視する必要があります。
席に座っている状態でも、足をブラブラさせたり、前の座席についているテーブルをパタンパタンと出したりしまったりすると、振動が前の人の座席に伝わって不愉快な思いをさせてしまうのでNGです」
Q.子どもには、そうしたマナーをどのように教えたらよいのでしょうか。
立石さん「車内で守るべきルールやマナーについて伝える際は、『今日は新幹線に乗っておばあちゃんの家に行きます。電車の中では静かにしましょう』と丁寧語を使い、かつ威厳をもって教えましょう。
子どもは、いつもと違う雰囲気で話される内容に注目します。参考にするイメージは、“遠足に出発する前の先生”です。また、外出前と乗車前に『いすに座っている子どもの絵』などを見せながら“お約束”するのも有効です。
せっかくの旅行時に怒ったり怒られたりしてしまうと、親も子どもも気分が落ち込んでしまうもの。ルールを守れるように、親が上手に導いてあげることを意識しましょう」
Q.子どもが騒いだ時、親がやってはいけないNG行為はありますか。
立石さん「車内で子どもが騒いでしまった場合、『電車の中だから大声を出してはいけないよ』『静かに座っていてね』と制すのは基本ですが、『隣のおじさんに怒られるから静かにしなさい』『ほら、怒られちゃうよ』『みんな見ているでしょ』などのしかり方はNGです。
公共交通機関で静かにしなければならないのは、利用者がお互いに思いやりを持ち、皆が快適に過ごすためです。親は『なぜ電車内では静かにしていなくてはならないのか』の正しい理由を子どもに教える必要があります。周りの利用客を悪者に仕立てるようなしかり方は、トラブルの原因にもなりうるため控えてください。
また、席で泣き叫ぶ子どもをしかるのは逆効果です。どうしても泣き止まない場合、子どもを連れてデッキに移動するなどいったんその場を離れましょう。子どもも気分転換できます。泣き叫ぶ子どもを席に放置し、知らん顔をするのは論外です」
親と周囲の乗客の双方が意識すべきことは?
Q.子ども連れで新幹線に乗る際、準備しておくべきものはありますか。
立石さん「車内で遊べるおもちゃを持参しましょう。いつも家で遊んでいるものではなく、新しいものを用意して興味を引くのがポイント。乗車後、子どもがぐずり出したら『静かに遊ぼうね』と約束しておもちゃを差し出しましょう。携帯しやすいミニサイズの絵本もお勧め。折り紙も折って遊べるだけでなく、絵を描くこともできてかさばらないので便利です。
また最近は、親の携帯電話やタブレットで動画を見るのが好きな子どもも増えていると思います。いつもは動画視聴を短時間と約束していても、乗車時だけは特別に『長時間使ってもいいよ』とするのもよいでしょう」
Q.子ども連れの親と周囲の乗客の双方が意識すべきことは何でしょうか。
立石さん「親にとって、小さい子どもとの移動は非常に大変です。特に、新幹線のように、長時間静かに座っていなければならない環境下では、子どもは『眠い』『動きたい』などの理由でぐずったり、泣いてしまったりするものです。
ほとんどの乗客は気に留めないか、『ママは大変だなあ』と思うものですが、それに甘えて『子どもは泣くものだから』と開き直るのはNGです。通路で騒いだり、イスの上に立って遊んだりして、他の乗客に迷惑をかけている状況にもかかわらず、子どもに注意しなかったり、目を離したりすることもマナーに反します。
当然、混雑時の新幹線には子どもの泣き声が苦手な人も乗車しているはずです。特にグリーン車には、追加料金を払ってでも快適に休みたい人が多く乗車しています。そのような車両で『子どもだから泣いても仕方ない』という態度でいたら白い目で見られてしまいます。『公共交通機関はさまざまな人が利用する』ことを頭に入れて行動することが大切です。
まれに、子どもの泣き声を『うるさい!』と怒鳴ったり、『静かにさせろ!』と文句を言ったりする人を見かけることもあります。誰しもかつては赤ちゃんだった頃があり、公共の場で少なからず迷惑をかけながら成長してきたのですから、あまり敏感に反応しないでほしいものです。
子ども連れの親子と他の乗客の双方が車内で気持ち良く過ごせるように、お互いに節度ある態度を心がけましょう」
(ライフスタイルチーム)