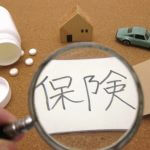最近では離婚自体が珍しいことではなく、ひとり親世帯も厚生労働省の「全国母子世帯等調査」をみると、年々増えています。
しかし、一方で日本のひとり親貧困率が主要国ワースト1に陥っている現状もあります。
今回はシングルマザーのゆうママさんのお悩みにファイナンシャルプランナー豊田真由美先生が回答します。
今回の相談者:フルタイム正社員のシングルマザーさん

現在都営住宅で5歳、3歳の兄弟を子育て中のシングルマザーです。
仕事はフルタイムの正社員で収入は約35万。元旦那からの養育費は止まってます。昔からずっと一戸建てで子育てすることが夢でした。
ローン審査もほぼ通りかけている段階で、親に「せっかく都営住宅に安く住めているのに。」と言われ悩んでいます。
(ゆうママさん / 30代女性)
まずは子どもの養育費の確認を!
シングルマザーでも家を買っている人たくさんいます。
わたし個人の意見としては「人に言われる必要ないですよ。」と言いたいです。
ただ、相談者さんの場合ひとつ気になることは、これからかかる子どもの教育費です。
離婚した元夫からの「養育費が止まっている」というのは、実は大きな問題です。
たとえ別れた相手でも、子どもを養育する義務があります。
元夫とは関わりたくないし、そんな奴のお金は使いたくない。
気持ちはわかりますが、養育費をもらわないのはダメです。子どもの権利ですから。
子どもが小さい今は保育料くらいで済みますが、中学・高校で塾などに通い始めると、すごい勢いでお金が出ていきます。
大学などに通うときには国立・自宅通学でも学費は400~500万円かかります。
シングルマザーだからと関係なく、いずれキツイ時が来ます。
基本的には相手にしっかり支払ってもらう

離婚合意書などに、養育費が支払われないときのルールも明記して、公正証書などにしておくか、あえて調停離婚をしてルールを決めておくことで、不履行の際には、家庭裁判所に申し立てて、相手のお給料から天引きしてもらうこともできます。
そこまでしてでも子どもの権利を守らないと、子どもの将来の選択肢が狭くなります。
しっかり試算して問題なければ迷う必要なし!
家を買ってやっていけるかどうかは、こちらをしっかり確認し、無理がないと確認できれば、迷う必要はなし!
STEP
- ローンがどれくらいになるか計算する
- 今の家賃の代わりにローン金額を置き換えた上で、家計が成り立つかどうかしっかり確認する
- 購入後の家計簿を試算し子どもの教育費などの貯蓄がどれくひとり親のらい出来るかを計算する
相談者さんは、戸建てに住んで子育てがしたくて、それが長年の夢でもあるわけです。
経済的にも将来にわたって問題がないのであれば、そこは人の意見に左右されずに考えた方がいいと思います。
老後まで考えるのであれば、私個人の意見ですが、持家の方が得だと思っています。物件選びも重要になるかと思いますが。
子どもの教育費は別で貯蓄する

子どもの教育費ですが、家庭の貯蓄とは別に考えないといけません。
高校卒業後も大学や専門学校へ行けるようにしたい場合は、子ども1人あたりの貯蓄額は300万~500万ぐらいを目安に用意しておいてあげましょう。
出来れば、子どもが中学卒業までに貯めるのがベスト。
あくまで目安ですが、このくらい貯めておいてあげると、将来の選択肢が広がります。
生まれた時から児童手当等を貯めているだけで15歳になる頃には1人200万円近く貯まります。
まずはこの児童手当金を死守しましょう。
プラスお年玉の一部やお祝い等を貯めておけば、300万近くにはなります。
親は100万~200万ぐらいを自分で貯めてあげたら良いのです。
かかるお金と貯めるお金を勘違いしない
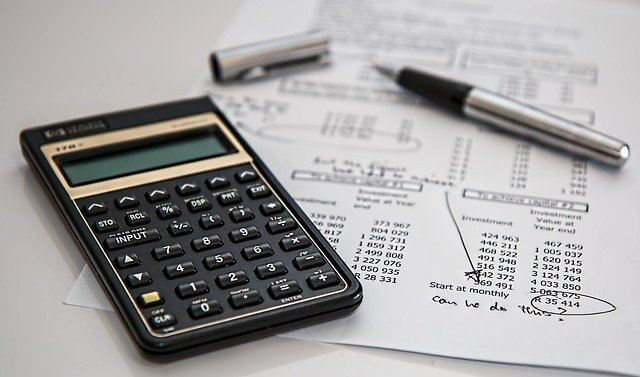
よく大学の学費は進路や下宿するかどうかで500万~1000万かかるなどと言われますが、勘違いしないで欲しいのは、あれはかかるお金。貯めるお金はそこまでなくても大丈夫なのです。
将来、一部に奨学金を利用してもらうとか、家計からも捻出してもらい、さらには子ども自身のアルバイトもできます。
ただ、私立+理系+下宿だと一番お金がかかります。芸術系・音楽系の大学だともっとかかる可能性も。
とにかく下宿代が大きな負担になるので、地方の方は大学時代にすごく学費がかかるのです。
しかし、大学の費用は親が全額出す必要もありませんし、かといって子どもが高額の奨学金を背負うのも大きな負担になるので、利用しても月3万~5万円までに抑えたいところではありますが、今はそうやって親子で協力し合う時代です。
最近は大学の給付型奨学金(返済しなくても良い)も増えています。
海外留学に行きたいと子どもが言った場合、留学対象の給付型奨学金もありますし、提携大学への交換留学制度がある大学もあります。
とにかく児童手当だけでも死守して教育費として取っておく。これを家計に入れない状態で住宅購入後の生活が成り立つかどうかを検証し、結論を出したらいいといいと思います。