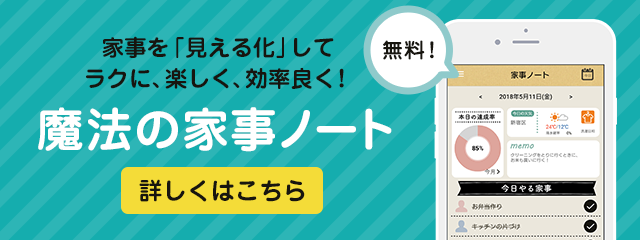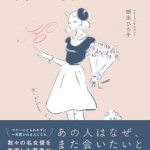日本列島全体が梅雨入りし、しばらくは「傘」を手放せない日が続きますね。
普段、何気なく使っている傘ですが、毎年この時期になると傘を原因とするトラブルが多発しています。多くの人が傘を持ち歩くこの季節、傘を使用する場合に注意すべきことは何でしょうか。
オトナンサー編集部では、お互いを思いやることでトラブルを防ぐ「真心マナー」を伝え、企業の人財育成やNHK大河ドラマ・映画などのメディアで活躍するマナーコンサルタントの西出ひろ子さんに聞きました。
人とすれ違う時は傘を傾ける
まず、傘をさす際に気をつけるべきポイントは何でしょうか。
「傘は頭の上でまっすぐさしましょう。そうすることで、周囲の人に傘が当たってけがをさせるなどのトラブルを回避できます。傘の柄を肩にかけて歩いたり、立ち止まったりしてしまいがちですが、それでは、ほかの人の邪魔になってしまいます」(西出さん)
また、人とすれ違う時は、自分の傘が相手に当たらないように少し傾けてあげるのがポイント。お互いに会釈をしながらすれ違えば悪い気持ちになりません。
電車やバスなどの乗り物や、お店など建物の中に入る場合、傘を畳むことは当然ですが「畳む前に、傘についた雫をはらいましょう。この時、周囲に人がいないかどうかを確認すること。雫が人に降りかかってしまったら本末転倒です」。
濡れた傘はカバーに入れれば、たとえば満員電車の中で、自分の濡れた傘がほかの人の洋服を濡らすことはありません。「最も安全なのは、カバーに入れてカバンの中にしまえる折りたたみ式の傘です」。
お店にあるビニールカバーを利用
カバーがない傘の場合、カバーを別途購入するかタオルを携帯して、濡れた傘をサッとふいてから乗り物や建物に入るのがベスト。また、お店の前にあるビニールのカバーを使用後に持ち帰り、そのまま利用するのも一案です。これらの場合は、濡れたタオルや使用済みのビニールカバーを入れておく専用の袋(レジ袋など)を持ち歩くようにします。
ただし、お店を利用しないのにビニールカバーを持ち帰ると「マナー違反を越えた窃盗罪になる可能性」(リバティ法律事務所の塩野正視弁護士)もあるため要注意です。
「面倒かもしれませんが、ひと手間をかけることで、他人も自分も不快になるトラブルを防ぐことができるほか、床が濡れて転倒するといった危険も回避できます。一人一人の、ほんの少しの気遣いによる『真心マナー』で心地良い社会にしたいものです」
(オトナンサー編集部)
マナー西出ひろ子
マナーコンサルタント、マナー評論家、マナー解説者、ヒロコマナーグループ代表
マナー西出ひろ子としても活動。大妻女子大学卒業後、国会議員などの秘書職を経て、マナー講師として独立。31歳でマナーの本場英国へ単身渡英。オックスフォード大学大学院遺伝子学研究者のビジネスパートナーと起業し、お互いをプラスに導くヒロコ流マナー論を確立させる。帰国後、名だたる企業300社以上にマナー研修やおもてなし、営業接客マナー研修、マナーコンサルティングなどを行い、他に類を見ない唯一無二の指導と称賛される。その実績はテレビや新聞、雑誌などで「マナー界のカリスマ」として多数紹介。「マナーの賢人」として「ソロモン流」(テレビ東京)などのドキュメンタリー番組でも報道された。NHK大河ドラマ「いだでん」「花燃ゆ」「龍馬伝」、映画「るろうに剣心 伝説の最期編」などのドラマや映画、書籍で、マナー指導・監修者としても活躍中。著書は28万部突破の「お仕事のマナーとコツ」(学研プラス)「マナーコンサルタントがこっそり教える 実は恥ずかしい思い込みマナー」(PHP研究所)「運のいい人のマナー」(清流出版)など監修含め国内外で95冊以上。「10歳までに身につけたい 一生困らない子どものマナー」(青春出版社)など子どものマナーから、ビジネスマナーやテーブルマナーなどマナーのすべてに精通。2021年最新刊「入社1年目の新しい教科書 新・ビジネスマナーの基本とマナー」(学研プラス)は発売前から好評。ヒロコマナーグループ(http://www.hirokomanner-group.com)、プレミアムVIPマナーサロン(http://www.erh27.com)。
※「TPPPO」「先手必笑」「マナーコミュニケーション」は西出博子の登録商標です。