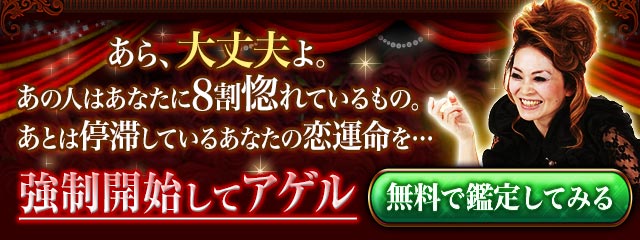「運動神経の良い子に育ってほしいな」
そう願うママも多いはずです。私自身、運動に関して良い思い出がないので、尚更そう思います。
その反面、「私に似て運動音痴になってしまうのではないか」と不安にもなります。
果たして、運動神経は遺伝なのでしょうか?
運動音痴にさせない方法ってあるのでしょうか?
運動神経は親から子には遺伝しない?

最近の研究結果を見てみると、人間の脳は3歳までに80%、6歳までに90%、12歳までに100%完成すると言われています。
そして、運動神経を良くするためには、脳の発達段階に合わせて運動の種類を変えていくことが大事なのだそうです。
つまり、運動音痴は遺伝しない!
そして、運動音痴になるかどうかは年齢に応じた遊びをできるかどうかにかかっていそうです。
子どもを運動音痴にさせないためには?年齢別:オススメの運動法
年齢別におすすめの運動法をみていきましょう。
子どもを運動音痴にさせないための運動法:乳児期は「赤ちゃん運動」が大事!

寝返り・腹ばい・ハイハイ・つかまり立ちといった「赤ちゃん運動」には、
- 歩く
- 走る
- 正しい姿勢を保つ
など、1つ1つに大事な意味があるそうです。
狭い住環境で過ごす子どもはハイハイの期間が短く、すぐにつかまり立ちができてしまうケースも多いようですが、ハイハイは腕や胸の筋力アップや、環境の把握、脳の発達にもとても効果的だそうです。
たまには広い環境で遊ばせるのも、いいですね。
子どもを運動音痴にさせないための運動法:1~2歳はボール遊び!

歩くようになって、一人遊びもできるようになるこの時期はボール遊びがおすすめです。
1歳くらいの時期はボールを追いかける、蹴る、投げるなどの動作を覚えます。
2歳くらいになるとボールが弾む動きがわかるようになるので、ボールを走って追いかける、という大事な運動ができるようになります。
子どもを運動音痴にさせないための運動法:幼児期はバランスがポイント!

動くことが上手になってくる3~6歳の時期はバランスをとる動きが大切です。
幼児期から養われたバランス感覚は、その後のどんなスポーツにも役立つようです。
例えば「ケンケンパー」といった懐かしい遊びを一緒にやってみたり、ブランコや滑り台などの遊具を使ったりして遊びましょう。
子どもを運動音痴にさせないための運動法:小学校低学年は動きの基礎を!

動きの基礎となるものは「歩く・走る・投げる・捕る・転がる・跳ぶ」だそうです。
鬼ごっこを通しての全身運動や、相撲・縄跳び・キャッチボールを通して力の使い方やバランス感覚が身につきます。
伝統的なコマ・けん玉は投げる動作を身につけさせる最良の遊びです。
年齢に合わせて自由に運動して、たくさん失敗や経験をして、健やかな体に育てたいものですね。
二児のママ。子育て応援ZEROSAI代表。
長男の出産をきっかけに、子育て支援をはじめ、高知県内外各地で子育てイベントを開催しています。
その中で、いかに、育児と家事を楽しむか、息を抜くか、手を抜くか(笑)毎日奮闘しています。
子育て応援「ZEROSAI」