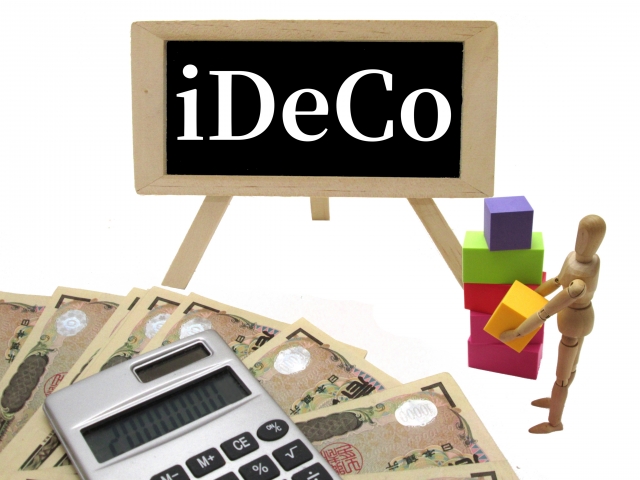
前回、iDeCoの特徴について書かせていただきました 。
今回は、巷で言われているiDeCoのメリット・デメリットについて考えてみます。
まず メリットについてですが、多くは「税制優遇」にあります。
iDeCoのメリット1:掛け金が全額「所得控除」される

iDeCoで積み立てた掛け金は、全額が所得控除され、所得税・住民税が安くなります。
所得税額は、所得金額に税率をかけて計算します。iDeCoの掛金は、所得から差し引かれる(控除される)ため、それだけ税金が安くなるのです。
たとえば、単純化した例を示すと、500万円の所得がある人が年間15万円の掛金を払った場合、500万円ではなく485万円に税率をかけて所得税が計算されることになります。
会社に勤めている方は月々の給与から源泉徴収されていますが、年末調整や確定申告をすることで、所得や掛け金に応じて納めた税金が戻ってきます。
iDeCoのメリット2:運用中に得た利益も非課税

運用期間中に得られた利益にも税金がかかりません。これも大きなメリットだといえ ます。
株式や投資信託で得られた売却益や分配金、預金の利息には20.315%(=所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税金がかかります。
しかし、iDeCoで運用した場合には、こうした税金がかからないのです。
利益から税金が差し引かれることなくそのまま運用に回せるので、複利効果が期待できます。
つまり利益が利益を生み、雪だるま式に資産を増やすことが期待できるのです。
iDeCoのメリット3:運用資産の受け取りには「退職所得控除」「公的年金等控除」が適用

さらに、60歳を迎えて運用した資産を受け取る際にも、節税メリットがあります。
運用した資産は60~70歳までの間に、「一時金」「年金」「一時金と年金の両方」の3つのいずれかの形式で受け取れます。そのいずれを選択したとしても、税金の優遇が受けられます。
一時金で受け取れば「退職所得控除」が、年金の形で受け取れば「公的年金等控除」が適用され、所得税が安くなるのです。
iDeCoのメリット4:運用する金融商品のコストが低い

投資信託については以前から何度も触れてきました。その際、信託報酬や購入手数料などのコストを意識しようと書いてきました 。
iDeCoの運用は投資信託を中心にすることが多いと思いますが、iDeCoで取り扱われている投資信託は、一般に販売されているものに比べて、信託報酬など運用期間中にかかるコストが低いものが多いのです。
また、購入手数料についても、iDeCoで取り扱われている多くの投資信託にはかかりません。
iDeCoは長い期間をかけて運用するのが基本になります。コストが低いほど、その分効率的な運用ができ、成果も大きくなっていきます。
最後に、巷でデメリットだと言われていることに触れておきます。
iDeCoのデメリット:60歳まで運用中の資産を引き出せない

60歳になるまで積み立てた資産を引き出せないだけではなく、途中で解約することも原則認められていません。
しかし、本当にデメリットでしょうか?
iDeCoの目的は「老後資金を積み立てる」ことにあります。この目的のためには、60歳まで引き出せないのは当然のことだと思います。
税制優遇でメリットが大きいからといって、iDeCoですべての資産を運用するようなことはおすすめできません 。
つみたてNISAや他のさまざまな制度と組み合わせ、自分にとってよりよい資産形成のポートフォリオを作っていきましょう。
中小企業診断士、ライター。転職を繰り返していたため、他人より退職金が少ないことに不安を覚え、2008年ころより資産形成のために投資信託を活用した金融投資を開始。当初はインデックス投資を中心に運用していたが、徐々に投資哲学に共感できるアクティブファンドに軸足を移す。ただし、積立を基軸とする「コツコツ投資」のスタイルは維持している。
中小企業診断士兼ライターとして多くの経営者にインタビューさせてもらう中で、成長する経営者の「お金に対する哲学」を学ぶことができた。
現在は、経営者の資産形成のアドバイスもできるようになることを目指している。
主な執筆先は、クーリエジャポン、企業診断(同友館)、道経塾(モラロジー研究所)、など
















